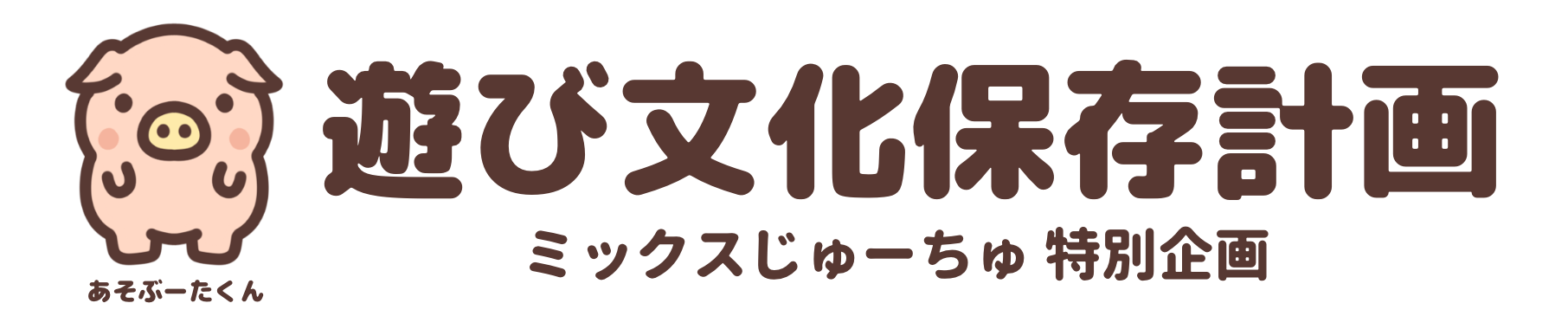1951年生まれ
1951年生まれ 「学校の下校時」飴細工のおじさんの思い出
katsuさん兵庫県 1951年生まれ 男性学校の下校時に校門を出て塀ぞいに少し歩いて行くと、飴細工のおじさんがいました。自転車の荷台には飴で作った金魚、うさぎ、カメ、等が棒に刺して並べて有る箱を乗せていました。箱の引き出しには色々な品物が入ってました。リクエストによっては何でも作るよとおじさんが子供達に講釈して売ってました。生意気な子が多分おじさんには出来ないだろうと思い「龍」を注文しました。おじさんもちょと難しいそうな顔してましたが、早速一塊の飴を出しバーナーで炙りながら火鉢みたいので引っ張ったり曲げたりして形にして行きました。龍の顔は難しいそうで細かい作業をしていましたが最後に髭を作って完成しました。注文した子に棒を刺して渡しました。僕は小遣いを余り持って無かったので、薄い板状を舐めて動物の形を抜き出させる飴と水飴を買いました。水飴は硬い透明な飴状な物が二本の箸に巻いてあるだけの飴です。それを何回も何回も捏ね回していくと、少しずつ柔らかくて美味しい飴に生まれ代わります。それを舐めながら家に帰りました。