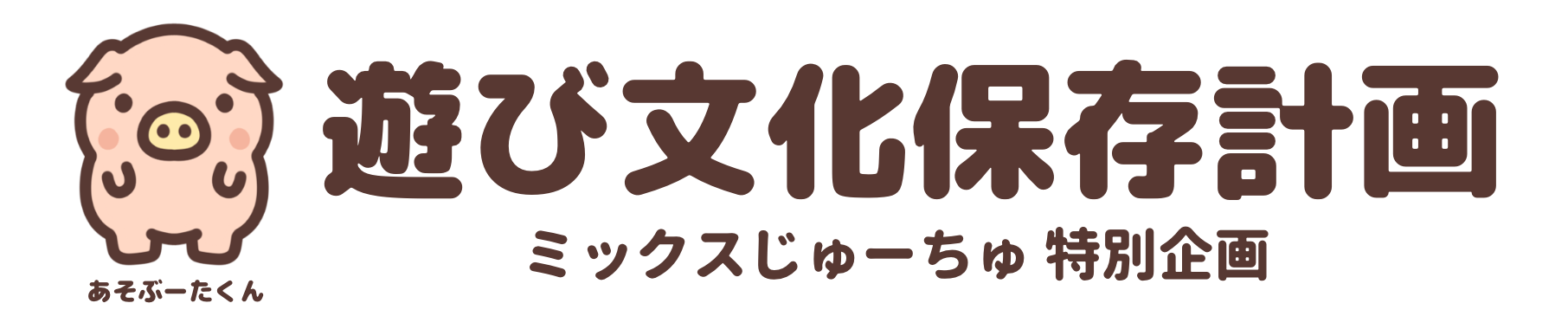1987年生まれ
1987年生まれ 寄り道の思い出
エリックさん沖縄県 1987年生まれ 男性通っていた小学校から自宅まで、子供の足で40分位の道のり。家が近所でいつも一緒に帰る仲良しメンバーがいました。いつものように帰っていると、友達が『俺、近道見つけたってば』と言って、いつもの道から少し外れ、林みたいな森みたいな崖に案内してくれました。今考えれば、人が通った形跡もなければ、確実に遠回りになることは明らかでした。しかし、その時の僕らはその友達の話を疑いもせず、むしろ冒険心が勝り、皆んなで競争して崖を登ったのを覚えています。木の枝に刺さったり、足を滑らせ落ちそうになったりしましたが必死で登りました。そしてついに頂上まで登り着いたら…使われていない畑と井戸、古い木造の家がありました。今まで知らなかった場所だったからか、登り切った達成感からなのか、なぜか、気分が上がりまくったのを覚えています。そこで僕たちは『ここを秘密基地にしよう』と考えました。その日から毎日のようにそこに行き、段ボールや、マンガ、その他遊び道具を持っていき、集まって遊んでいました。結局、家までの到着時間はいつもの2倍以上かかっていました。