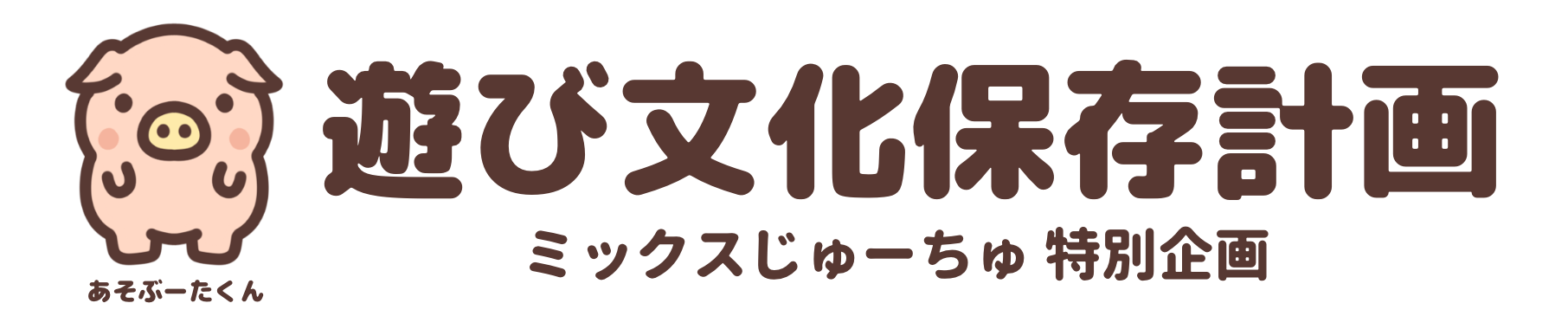1984年生まれ
1984年生まれ 「ゴムとび」と「ゴムダン」のルール
おかずさん岡山県 1984年生まれ 男性【ゴムとび】ゴムとびは、10人くらいでやっていました。100均で売っているような、パンツ用のゴムです。2人は両側で腰の高さくらいで持っていて、残り8人で順番に跳んでいきます。男とびと女とびがあります。男とびは、ゴムに対して平行に跳び、右足をあげてゴムを越え、その後左足もゴムを越えます。ゴムにあたっても、飛び越えられたらクリアです。女とびは、ゴムに対して垂直に跳び、右足、特に足首の部分を引っ掛けるようにして跳び、その後左足も同様にゴムを越えます。だんだん高くしていき、越えられなかったら脱落、最後の1人になるまで競います。走り高跳びのように助走をつけて跳ぶのではなく、ゴムの目の前に立って跳びます。【ゴムダン遊び】ゴムダン遊びも10人くらいでやっていました。2人は両側でかかとに引っ掛けて輪にしており、残り8人は輪の中にいます。グーで輪の中に足を入れ、パーで輪の外に足を出します。だんだんペースを速くして行き、間に合わなかったら脱落。最後の1人が優勝です。