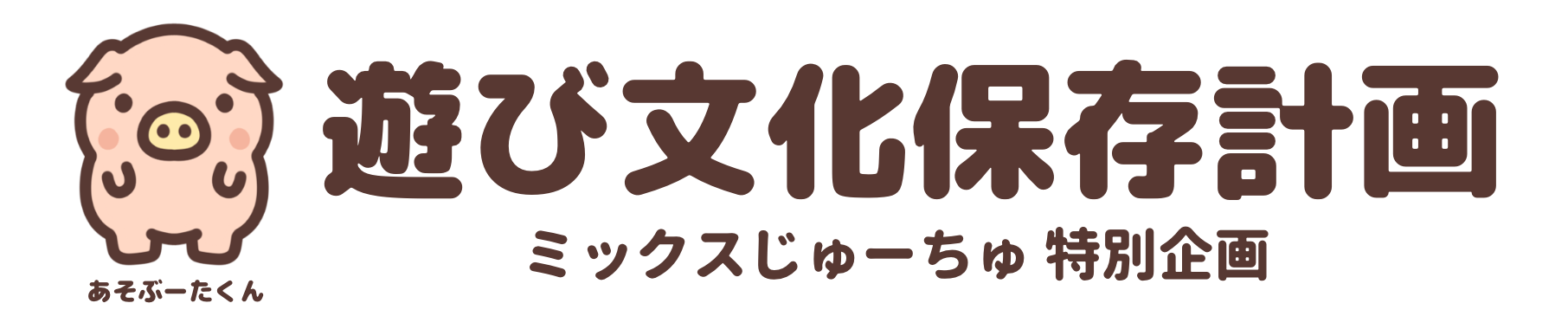1989年生まれ
1989年生まれ パチンコ台づくりの思い出
harukazuさん岐阜県 1989年生まれ 無回答小学校の時、夏休みの工作で何を作ろうかと悩んでいた時、友達と一緒に「パチンコ台」を作ろうという話になりました。一緒に材料を買いに行く中でビー玉をたくさん買い、玉の1つ1つの模様が違い、キレイに輝いていたことを覚えています。いつしかパチンコ台を作ることよりもビー玉を転がして遊ぶことに夢中になりました。友達と指ではじいて当たったビー玉を自分のものにできるというゲームを始め。何度も繰り返しながら自分の好きな色、模様の玉を集めるのが楽しかったです。不思議なものでお気に入りのビー玉は大切にしまっていたつもりなのに、いつの間にか無くなることがありました。どこかで落としたのか、転がって隙間に入ってしまったのか分かりませんが、1つでも無くなったことに落ち込み。泣いてしまいました。