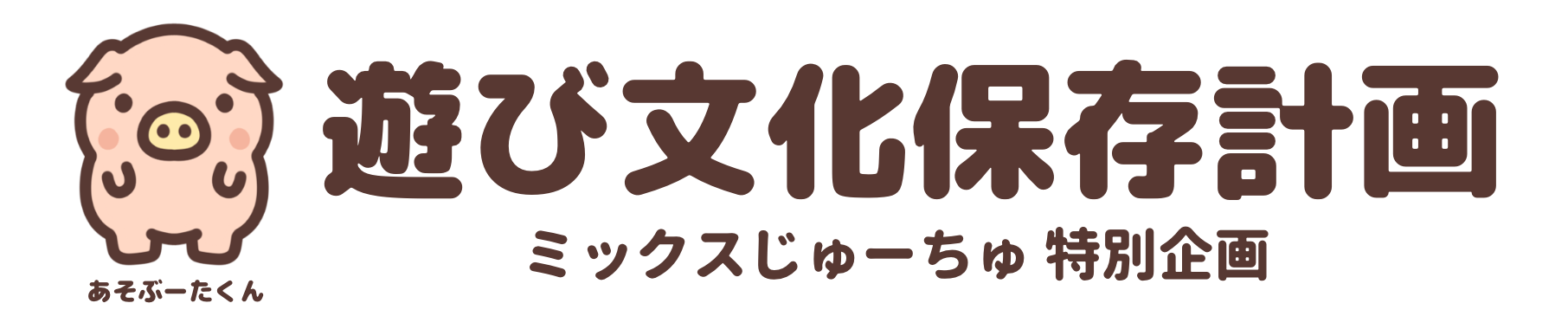1980年生まれ
1980年生まれ 「意図的に逃がした兎」夏休みの思い出
えつこさん自宅の畑 1980年生まれ 女性私は小学校3年生の夏休み、友達も少なく親も共働きで、あまりかまってもらえず、家でゴロゴロする毎日を送っていました。日中の唯一の話し相手はペットの兎1匹。よく母から聞かされていた兎とカメのおとぎ話を思い出し、私と兎、どちらが速いのか勝負をしたくなりました。住まいは田舎の為、自宅の敷地は広く裏庭は畑になっています。ペットの兎を抱っこして畑に連れていき、さあ、勝負だ!とペットの兎を逃がしては必死に追いかけ捕まえ…を繰り返して遊んでいました。もし捕まえられなかったら、そのままペットの兎はどこかへ逃げ二度と戻らないでしょう。そして親の可愛がっている兎を逃がしてしまったらコテンパに怒られることでしょう。というスリルが堪らなく癖になり、親に内緒でその遊びを続けていました。その為か、学年でも遅かった私の脚は速くなり、運動会のリレーでは1位、2位は当たり前にまで成長しました。