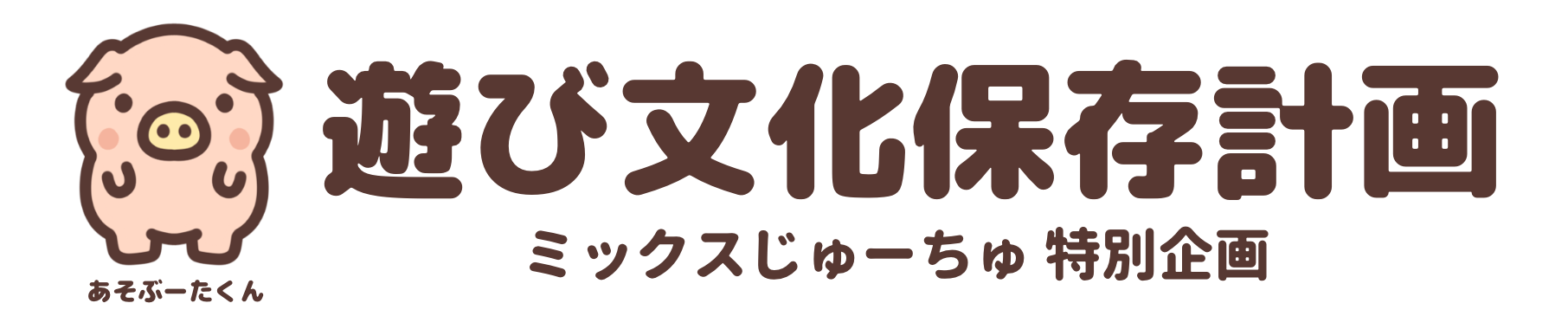1965年生まれ
1965年生まれ 「じゃんけん遊びの思い出」負けたら負けよあっかんべえ!
つううてさん埼玉県 1965年生まれ 男性小学校のときはよく、友達や兄弟とじゃんけん遊びをしました。よくゲームをする前にその順番を決めるためにじゃんけんをした記憶があります。かけ声は今とあまり変わらないと思います。「最初はグー、じゃんけんぽん!」です。そして、たまに「負けたら負けよあっかんべえ!」という言葉がかけられました。負けたら、変な顔を見せて友達らを笑わせるというルールがありました。今で言う変顔のことです。じゃんけんは何故か、同じ手を使い続けると勝率が上がった記憶があります。パーならずっとパーばかり、たまにチョキを入れたりしました。じゃんけんに負けたときの罰ゲームみたいなものもありました。当時はデコピンと言っていました。今も存在するのかわかりません。負けた場合、勝者は利き手をつかい、手のひらを敗者のおでこにあてて、中指をパチンっとあてる方法です。力の弱い人だとあまり痛くないですが、指の太い力持ちにされるときは怖かった思い出があります。