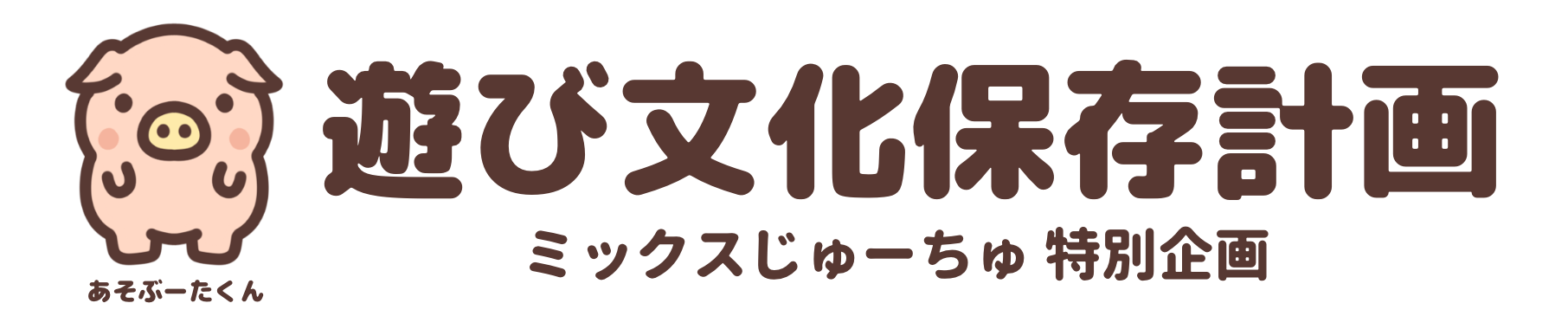1994年生まれ
1994年生まれ たまごアイス
オニササさん新潟県 1994年生まれ 女性校門前でアイスを売っているおじさんがいました。味は1種類。自家製のアイスで食感はシャーベットに近く、優しい黄色が印象的でした。何の味、と例えられないのですが、ほんのり甘かったです。アイス自体に決まった名前はないのですが、子どもたちの間ではその色味から「たまごアイス」と呼ばれていました。価格はカップが300円、コーンが100円、モナカ(モナカの皮にアイスを挟んだ状態)が100円と小学生にも手を出しやすい価格です。子どもたちに大変好評で、文化祭や運動会のときは必ず出店していたのですが、長蛇の列ができていました。売っているおじさんは無口で必要最低限のことしか話しません。近所にお住まいだったので顔見知りではあったのですが、誰にもレシピを教えてくれませんでした。おじさんが体調を崩されてからは奥さんが代わりに売り子をしていました。奥さんも体調を崩されてからは、もう味わえないのが残念でなりません。