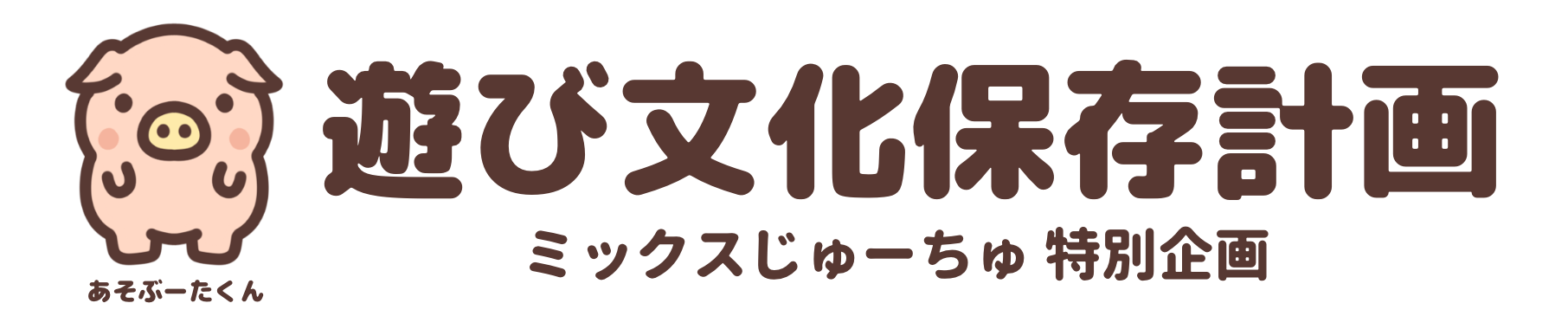1979年生まれ
1979年生まれ 駄菓子屋のベーゴマ
おむすびさん香川県 1979年生まれ 男性小学校の頃でした。近所におばちゃんが営んでいた駄菓子屋さんにベーゴマがありました。その頃はガンダムのプラモとかエアガンが人気で、ベーゴマはすでに昔のおもちゃ枠になっていたので、見向きをすることもなく素通りをしていました。私は小学校のクラブ活動で工作クラブに入っていました。私が工作クラブに入ったのは、好きなプラモデルを月に一回学校に持って来て作る名目で、親にプラモを買ってもらうためでした。工作クラブでは上級生の子たちがベーゴマ対決をしていました。上級生の子たちはある程度プラモ作りも終えて、違う遊びを色々やってみたかったんだと思います。大掃除に使うワックスが入っていた筒形のカンカンに布を張り、その上にお互いベーゴマを落として先に止まるか、はじかれて落ちた方が負けという「喧嘩ゴマ」のルールでした。私もお小遣いを握りしめ、駄菓子屋でベーゴマを買って練習をしたのを覚えています。上手く回すのに苦労しましたし、カンカンの上にコマを落とすのにも苦労しました。今となっては良い思い出です。100均にあったベーゴマを買って、子供に回し方を教えたりしています。