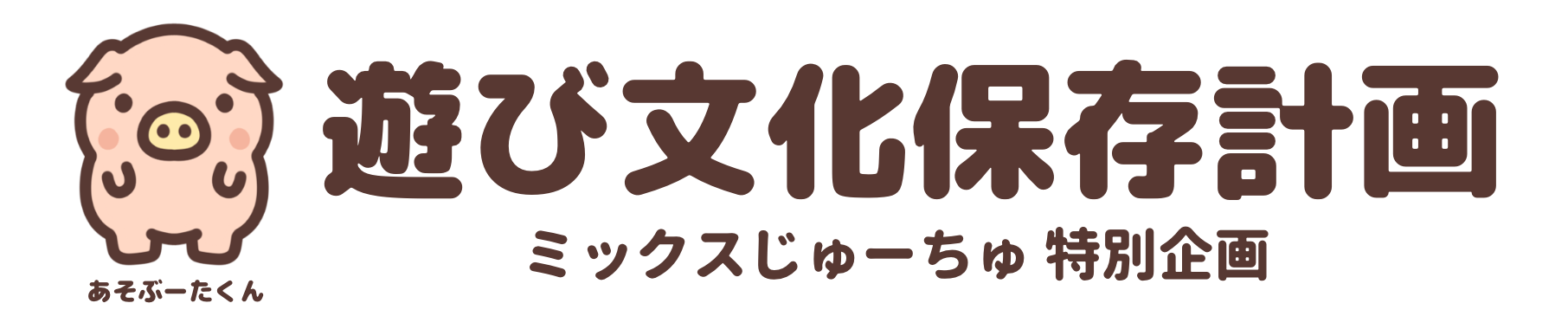1955年生まれ
1955年生まれ 小学校の帰りの「型抜きの思い出」
DYさん東京都 1955年生まれ 男性思い起こせば小学校の頃です。当時のお小遣いは10円とか20円くらいで、100円を持って居る子はいませんでした。うちの家族は人数はいっぱい居たのですが、おばあちゃんが働きに出ている、おやじは1週間に1〜2度しか返ってこない(仕事が忙しいのと、少々遊んでいたようでした)、母親は結核で入院、一緒に住んでいるおじさん2人は大学生と高校生という状況での小学生でした。毎日貰った少々の小遣いを必死にためて、学校の帰りに何を買うのか楽しみにしておりました。1週間に1回くらいの割合で駄菓子屋や学校の前でおじさんが出している店に興味深々で行き、何かを買って帰るという生活です。今思い出されるのは小学校の校門の裏に自転車で店を出していた、型抜きのお店です。見本の形通りにウエハーみたいな台紙からハリの様な物でその形通りに形状を仕上げるというものでした。10〜20円程度の値段だったと思います。上手く出来ると飴とか、ソースせんべいの様なお菓子をくれるというものでした。チャレンジする形状の難易度によってもらえる物のレベルが上がります。楽しみはそのお菓子だけでなく、時間をかけてやる...つづき